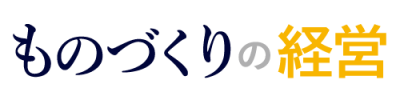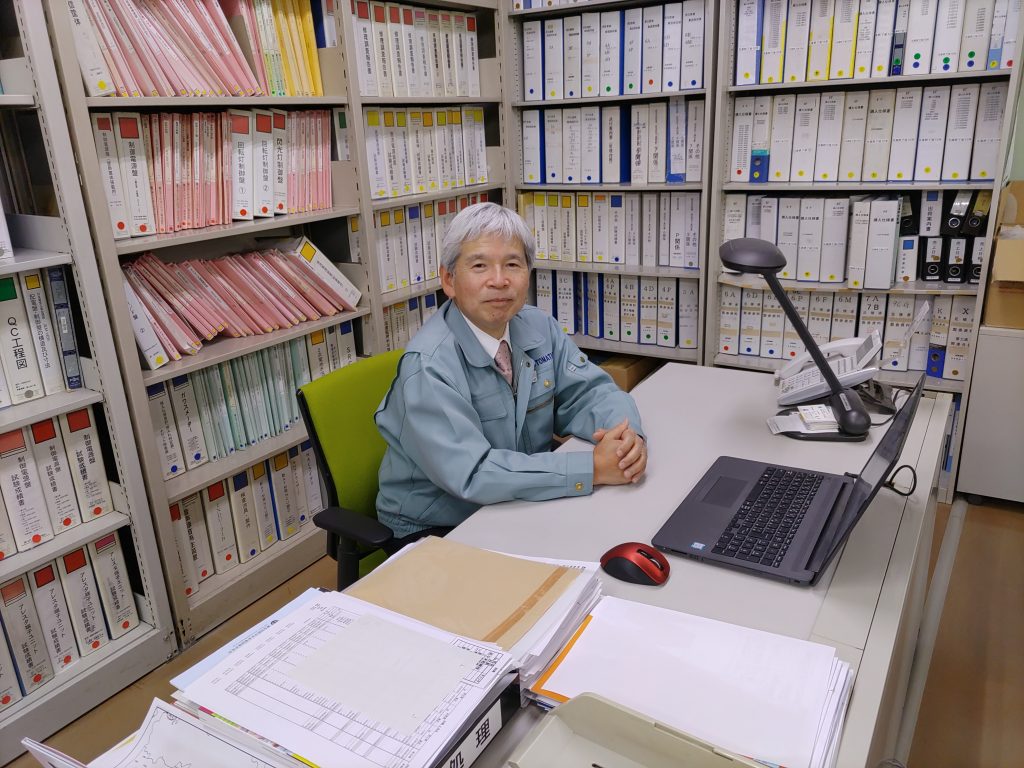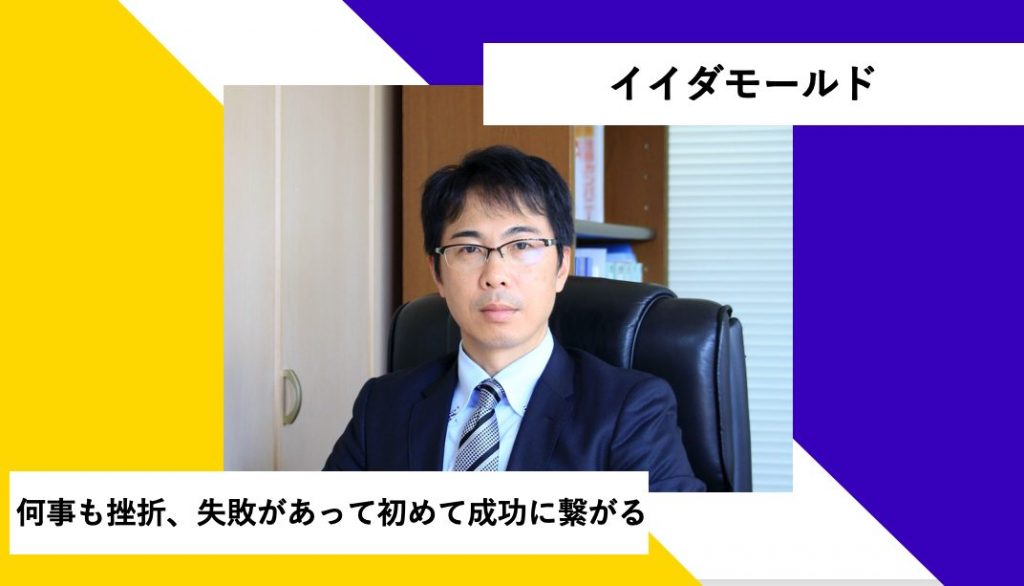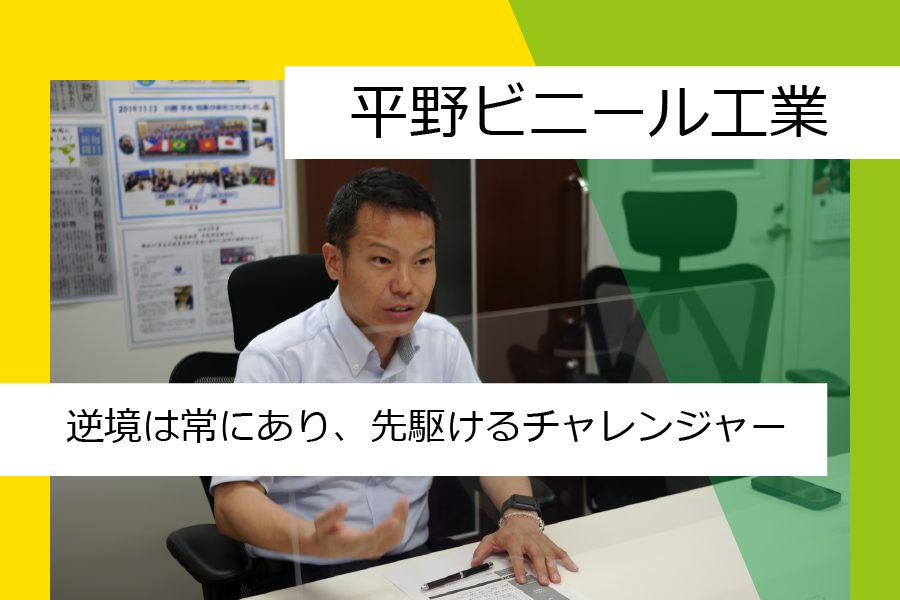大切なことは、向上心と好奇心のこの2つ。やっぱり面白がらないと成長しない
聞き手:編集部・渡邊 話し手:株式会社富士オートメーション 代表取締役社長 高窪 裕治様 埼玉県の富士オートメーション株式会社の高窪社長様、やっぱり面白がらないと成長しないと語る高窪社長。 2代目として社長業を引き継ぎ、苦境にも負けず会社の維持を成し遂げてきました。 今までの経緯と、社長独自の取り組みや今後の展望についてを詳しくお伺いしました! ―――本日はよろしくお願いします。はじめに、会社の概要や会社の取り組みを教えていただけますか。 高窪社長:1963年に浦和市(現さいたま市)で僕の父が創業しました。基本的には創業当時から、カスタムオーダーでエレクトロニクス分野におけるPC周辺機器・端末機・制御装置などの仕様検討から設計・ソフトウェアの開発、製造、試験、完成品まで一貫体制で行っています。僕の父が売っていた技術は、いわゆるデジタルの回路設計で、創業当時はちょうど世の中の電気製品がアナログからデジタルに変わる転換期だったので、デジタル回路設計の需要が「どうにもこれから伸びそうだ」ということで独立して会社を始めたというのが創業したきっかけです。始めた当初は、いろいろ売り込みしようかぐらいのことを考えていたみたいなんですが、独立前からお付き合いのあった企業様から「独立するならこれやって」みたいな感じで仕事を頼まれたらしいですね。 そのため、創業当時からご縁があって富士電機さんや大手企業様からのお仕事をいただいていたので、ある意味営業らしい営業をせずに、仕事をもらえていたと。言い方は悪いんですけども下請けとしてスタートして、そのまま下請けとして大きくなっちゃった感じです。 また、創業して数年で、富士通株式会社との付き合いができてきて、そこでやり始めた富士通・富士電機さん向けのインフラ関係の仕事の需要が伸びるのに合わせて、会社の業績も伸びて行ったっていう感じです。 目次 外国での生活、経験が僕の人生にとってはとても大きいものでした率先して自分が頭を下げる、嫌なことほど逃げない私は普通の人間なので、結局もう経験でしか乗り越えられない付加価値をいろんな場面で高めていかないといけない株式会社富士オートメーションについて外国での生活、経験が僕の人生にとってはとても大きいものでした ―――そうなんですね、そんな中で、高窪社長が2代目社長になるまでの経緯について教えていただけますか。 高窪社長:大分遡りますが、高校生の時に1年間オーストラリアに留学する機会があったんですね。外国での生活、経験が僕の人生にとってはとても大きいものでした。大学進学の際、父が会社を継ぐ必要もないし、好きなことをしていいよと言ってくれたので、海外経験から英語をもっとやりたいという気持ちで、英文科に進学し、大学卒業後は、英語を使える仕事をしたいという意思の元、富士通株式会社の海外事業部に縁があり、就職しました。 当時はバブルの直前で、特に富士通なんかも「海外にとにかくこれから事業を拡大していこう!」という時期だったので、そういう海外向けの人材をかなり採用してたんです。入社して7年経った頃、アメリカに駐在する機会がありまして、結婚したばかりの夫婦2人で2年間アメリカに駐在してきました。 当初は5年間の予定だったんですが、当時はそのアメリカが不況の真っ只中で、私が出向した会社もあまり業績が良くなくて、結局他社に売却をすることになっちゃいまして、2年で帰ってきちゃったんですよ。で、帰っては来たものの、あんまり仕事でやることはないんですよね。大会社だったので、クビにこそならなかったんですけれど、残念ながら、どこかの部署の手伝い的なポジションになってしまって。あまり面白くないなと思っていたところに、父のほうから「だったら会社手伝うか」みたいな話になって、それでうまくまんまとそれに乗せられて(笑)転職したのが34歳のときですね。 ―――文系で製造業に携わることに関して抵抗はありませんでしたか。 高窪社長:電気製品みたいなものは昔から好きで、ラジオキットなんかを組み立てたりとか、そういうのはちょっとやってた時期がありました。だから嫌いとかでは全然無いです。ただ、仕事にできるってほどの知識や技量とかは身に着けてなかったので、それをさすがにもう1回やり直すっていうのは厳しいなと思ってやらなかったんです。でも根っこのところでは製造業的なものってのは嫌いじゃなかったですね。 ―――世代交代したあと、ご苦労された経験はありましたか。 高窪社長:何か逆にね、ないです(笑) それは先代が、あんまり現場やお客さんのところに行かなかったからなんですよ。先代社長は現場をもう社員に全部任せちゃっていて。僕も社長になってからわかったんですけど、社長って社外活動がやたら増えるんですよ。父は社長業に加えて*ロータリークラブに入っていたので、もう社内にいるより社外の方が多いぐらいな感じで。そのおかげで、社長交代してもあんまり周りから、とやかく言われなくてですね、むしろ内部の方からは「やっぱり息子がやるよね」みたいな感じで安心されましたね。父が創業した当時に一緒に働いていた頃の仲間というのは、当時の時代的にも、週末とかになるとわが家に遊びに来てたりしたんですよ。なので、僕のことも子供の頃から知ってるんですね。だから社長の息子というのはマイナスの見方ではなくて、もう会社入ったんですね、社長になるんですね、みたいにプラスに見てくれた感じでした。逆に、僕と年齢が近かった人たちの方が、あの息子が突然入ってきて、すぐ役員になってみたいな感じの反発があったのは事実です。 率先して自分が頭を下げる、嫌なことほど逃げない ―――会社を継ぐ上で大事にしていた/している部分はどんなことでしたか。 高窪社長:入社してからは営業系の仕事をやることが多かったので、どうしても謝りに行くようなときがあるわけですよ。そういうときはとにかくもう率先して自分が頭を下げに行くとかね。嫌なところで逃げちゃうと、それは絶対ずっと根に持たれるなっていうのは見てきたので、嫌なことほど逃げないようにしようっていうのは常に心がけてました。会社に最初に入ったときは、自分がいつかバトンタッチする日のことを考えて、どんなことができるかなっていう考えでやったりもしてたんです。ですが、だんだん現実がわかってくると、「会社はやっぱりまず維持しなきゃいかんな」というのが、一番大事になってきまして。やりたいことをやって、そのままうまくいけばいいんですけど、うまくいかなかったときに会社ってやっぱり潰れるんだなっていうのがわかってきて。さすがに会社を潰すわけにいかないねってなってからはとにかく、維持継続が第一の目標になってしまいました。残念ながらというか、面白くない話ですけど。 ―――いやいや、、うまく行かないときというのはどういう状況か教えていただけますか。 高窪社長:やっぱり人間って自分の経験がまず基準になるものなんですね。会社に入ったときに同世代ぐらいの人がいて、そういう人たちを味方にして、やっていこうと思ったんですが、皆さん温度差がありまして。一緒にやりましょうと言ってくれる人もいれば、全然そういう話にのって来ない人もいるし、そもそも、言い方が難しいですけど、一緒に仕事することが、レベル的に難しいっていう人たちもいるわけですよ。 レベル的に難しいというのは、僕が「こういうことを考えてるんだけど」っていう話をしても、うまく伝わらない、自分と基準が合わないんです。そういうこともあって、最初は特に、誰を仲間にしてやっていけばいいのかっていうのがすごく難しかったです。 でも、正直未だに乗り越えてなくって、ちょっとうまく行きかけては思いがけないことが起こってまた元に戻ってみたいなのの繰り返しの方が多いですね(笑) 私は普通の人間なので、結局もう経験でしか乗り越えられない ―――経営者の抱える責任の重さがあると思うんですが、社長はどうやってこう乗り越えてきたんですか。 高窪社長:僕は普通の人間なので、結局もう経験でしか乗り越えられないと思っています。 例えば、社長になる前は、「会社に借り入れがいくらあるよ」って言われても、あまりピンとこなかったわけです。大変だな、ぐらいにしか思ってなかったんです。社長になって借り入れの保証人のハンコを押させられるようになって、その時に初めて「何千万という金額、これって、会社うまくいかないと全部自分のとこに来る、つまり自己破産だよね。」と、リアルに感じたんです。最初はそれがもう恐ろしいというか、単純に生活成り立たなくなっちゃうじゃんっていう感覚でした。でもその感覚を味わう回数を重ねて行くと、だんだんと何とかなるかなという感じになってきて、その都度その都度どうやって乗り越えればいいかっていうとこに頭が向くようになってきました。 結局よく言われるんですけど、命まで取られることってないので。ただ会社を維持継続していくためには、相手に、ここは何とか協力して欲しい、協力してもらわなければいけないっていうところをどれだけきちんと伝えるかっていうところが大事だと思っています。 金融機関だけとは限らないんだけど、何をやるにしてもどこまで粘れるかみたいなところがあって、例えば、お客さんとも、どこまで粘り強く交渉するかが鍵になってくるところがありますね。 ―――そうなんですね、では高窪社長の強みは粘り強さであると思いますか。 高窪社長:どっちかっていうと、粘り強さは、後天的なものですかね。そうせざるを得なかったのかな。どっちかっていうと本来僕は楽観的な人間なんで、何とかなるかというのが根っこに常にあります。自分でいうのもあれですけど、喋りはまあまあ上手い方だと自負しているところがあります。伝えたいことを伝えるっていうことに関しては、相手に誤解を与えずに、こっちの伝えたいことはちゃんと伝えられるかなっていうのは、強みだと思っています。 この強みが活かされる時って、大抵がトラブル対応の話なんですけど。例えば、お客さんからのクレームは大小様々あるものなんですけど、かつて大クレームが1回発生しまして、それで何千万円賠償しろ、みたいな話になったことがあったんです。それを払ってたらうちの会社も潰れちゃう、というようなことがありまして、それになんとか対抗しなくちゃいけない。それは本当にもう真剣に何日も考えました。どういう理論展開でいけばいいのか。うちの落ち度っていうのは限定的だと、ないとは言わないけど限定的だと。だからそれを100%うちのせいにされて全部補償っていうのは、そもそも論として間違ってるっていうことを伝えなきゃいけなかった。そのための理論武装をしてネタを揃えてどういうふうに誰に話をするかを考えてっていうことで、最終的には当初言われてたものの5分の1ぐらいになったのかな。ということで何とか耐えられる範囲で済んだっていうようなことはありましたね。 会社や社長さんによって違うと思うんですけど、うちの場合僕のところに報告が来るのはトラブルが起こってからなんですよ。本来は未然に防げるものは防ぎたいんだけど、大抵トラブルって起こってから報告が来ますよね。なんでこんなことになっちゃったの?っていう話がくるので、そこからどうやってリカバーするかっていうのは、もう非常に苦労していて、今でもしてます。(苦笑) ―――色々ご苦労がある中で、社長独自のリフレッシュ方法って何かあるんですか。 高窪社長:リフレッシュを特別意識してやっている訳では無いですが、サッカー観戦が好きです。地元の浦和レッズファンなんです。シーズン中はスタジアムに試合を見に行って、応援しながら楽しんでいるとストレス発散できますね。あと、学生の頃、吹奏楽をやっていまして、そのOBバンドに参加しています。OBだから、おじさんおばさんが集まって、合奏をやっています(笑) 合奏だから必ず人が集まるし、その後に必ず飲み会があることがいいですね。会社と全く関係ない人たちとの交流はリフレッシュできます。 ―――今後、会社をどう発展させていきたいと考えていますか。 高窪社長:ずっととにかく維持第一でやってきたので、あんまり発展という方向に気持ちが向かなかったんですけど、自分は技術者ではないですが、やっぱり世の中って技術がないと進まないなと思っています。なので、実際に現場で、ものづくりをする機会をもっと増やしていきたいなと思います。今はファブレスと言って、設計だけやって実際に物を作るのは海外の工場に頼んだりっていう会社が多いのですが、うちの会社の強みは工場を持って自分たちでものづくりをしていることだと思っています。確かにコストや効率などを考えると、固定費も増えるし、経営手法として決して褒められた方法ではないかもしれません。でも、「もの」を自分たちが作ることで、お客様から見える形で信頼してもらえると思っています。お客様が会社に来ると、こんなふうに「もの」を作ってるんだね、こういう人たちがこんなふうに作業してるんだね、というのが見えるので、その環境が信頼を得やすいと思っているんです。 特にコロナをきっかけに、リモート中心でリアルに会わなくても何でもできちゃう、みたいになってるじゃないですか。そういう時代だからこそ逆に、「やっぱり人間の手でものを作っている」ということは、もうそれだけでも価値があることだと思っています。 その価値を認めてもらい、かつ、現場作業は絶対無くならないので、現場の作業というものを、ちゃんと自分たちがやっていることを、評価してもらいたいと思っています。雇用自体もこれから継続的に維持できるといいなと。だから今まで以上に自分たちの手で作っていることをアピールしていきたいし、さらにそこからそれを作っている場所である、現場での作業の機会をこれからもっと増やしていきたいと考えています。 ―――他の会社にはない取り組みや会社独自の取り組みがあれば教えてください。 高窪社長:あんまりそういうノウハウがなく社長になったんですよ(笑) なので本から学んだりセミナー行ったり、あるいは先輩の経営者と話したりして、これだなって思うことは、結構取り入れてやっています。それともちろん社員からの意見も聞くようにしていて、だからそういう意味で何でも真似して、取り入れてみるみたいなところはあります。 例えば、一時間単位での有給取得を可能にしたことがあります。 うちの会社は製造業なのでタイムカードで時間管理をしているんですが、以前は最小でも半日単位でしか有給を取れなかったんですよ。ところがある社員から「一時間単位で取れないか」という要望がありまして。理由を詳しく聞くと、病院の先生の都合でどうしてもある曜日のこの時間にしか診察してもらえないというんです。会社を30分早く出れば何とか通院できるんだけど、30分早く帰るために、現状の制度だと半日休み出さなきゃいけないし、それだと有給がすぐ無くなっちゃうと。そこで検討した結果、一時間単位での有給取得が可能になるよう制度を変更しました。それが非常に好評で、うちは社員の平均年齢が高めなので、親の介護の問題を抱える社員もいまして、例えば親御さんをちょっと施設に預けてから来たりして、みんなの予定がフレキシブルに立てられるようになったことで、社員が喜んでくれています。会社としてもそういう意味で意外とそれがアピールポイントになったりしています。 社員の方からこういうことできませんかっていうリクエストがあれば、どんどん検討していきたいし、僕の方もこういうのやってみようよっていうのは、社員みんなに投げかけてやってるところがありますね。 付加価値をいろんな場面で高めていかないといけない ―――ちょっと話が大きくなりますが、日本の製造業が発展していく上で、必要なことや何かお考えがあれば教えていただけますか。 高窪社長:すごい大きな話からすると、日本が今のままで国として競争力を取り戻して、GDPでアメリカ、中国を覆すってことは残念ながらもう難しいと思うんです。今の円安もそうなんだけど、このままだと本当に没落国家になってしまう。確かに観光だのインバウンドとかあるんだけど、それって何が評価されてるかっていうと、日本の景色とかホスピタリティが安く楽しめるからですよね。最近ようやくそれが話題になってきましたけど、食事をして、5ドル掛からないみたいな。 ―――確かに、東南アジアと同じような価格帯で食事ができますよね 高窪社長:そう、例えばアメリカなんか行くと今お昼食べようと思ったら20ドル以上かかるわけですよ。日本はそうやってどんどん、安い国になっていってしまっている。そこからもう一度復活しようと思うと、やっぱり付加価値をいろんな場面で高めていかないといけないと思うんです。ただ、サービスの付加価値ってこれ以上増やすのは大変で、じゃあ何ですか、どうやって価値を高めればいいのって言ったときには、やっぱり「ものづくり」だと思うんです。あるいはそれをプロデュースするとか、とにかく今の価値水準を「もの」で上げて行かなきゃいけないと思うんですよ。それを支えるためにも、一般のいわゆる事業従事者の人たちがどのぐらいレベルが上げられるか重要だと考えています。 ―――この記事の読者の方に向けて、メッセージありますか。 高窪社長:大切にしている言葉は、好奇心と向上心。この二つです。やっぱり面白がらないと伸びないと思うんですね。目の前で起こってることが、これは何、どうやって作ってるんだろう、とかね。あるいは、このお客さんってどういうお客さんだろうなんだろうとか、そういう好奇心がないといろんなことを身につけられないと思うんですよね。あとは向上心というか、自分が持ってるスキルでも何でもいいんですけど、やっぱりちょっとでも良くしようと思ってないと、すぐ陳腐化しちゃう、というかおいてかれちゃうと思うんです。だから、自分の持ってる情報でも何でもアップデートするっていうことは必要かなと。なのでそれはもう新人に対してってことじゃないんですけども、いわゆる社会人みんなに送りたい言葉です。 株式会社富士オートメーションについて 株式会社富士オートメーションは、 お客様から「こんなモノをつくってほしい」「アイディアを製品化したい」といった相談に応じて、PC周辺機器・端末機など仕様検討から設計、ソフトウェアの開発、製造、試験、完成品まで一気通貫で行います。業務系アプリケーション、業務系以外の通信・表示機器設計のほか、PLCプログラミングにも豊富な技術と知識を備えており、BtoB開発パートナーとして様々なニーズに応えるモノづくりをトータルで提案しています。 エレクトロニクス分野における「設計、製造、試験」のあらゆる場面でお役に立てる、真の「エンジニアリング・サポート・カンパニー」を目指しています。 会社名:株式会社富士オートメーション 所在地:埼玉県 代表者:代表取締役 高窪 裕治 URL:https://fujiautomation.jp/